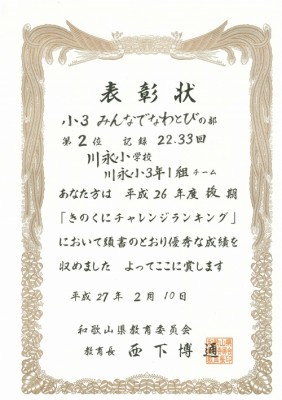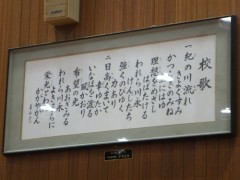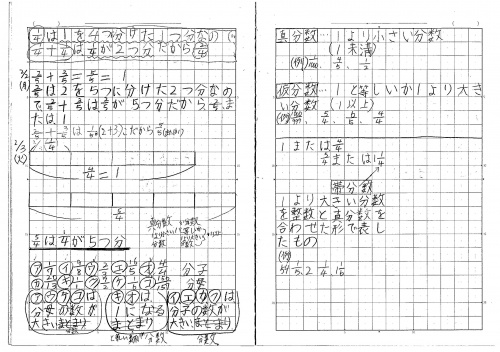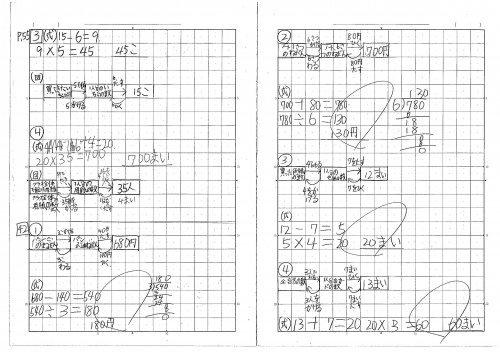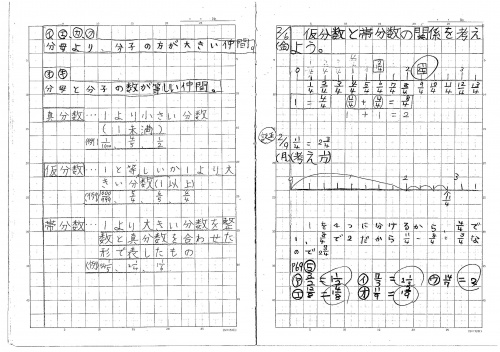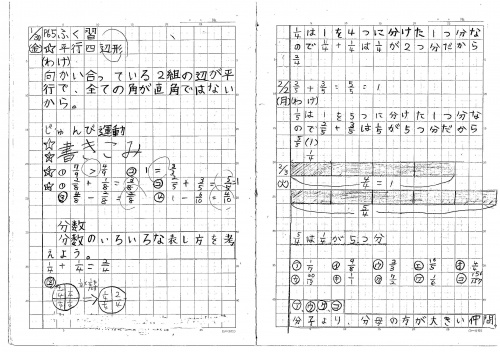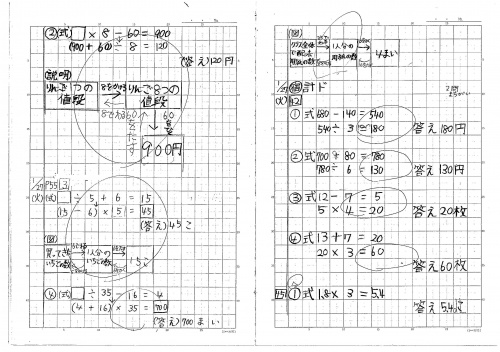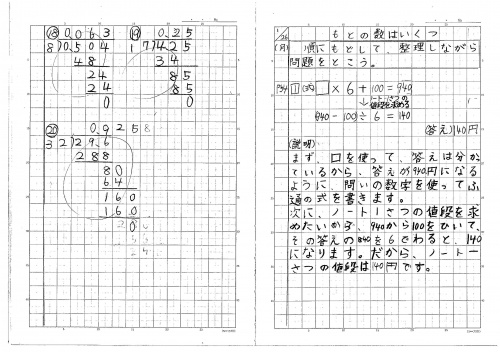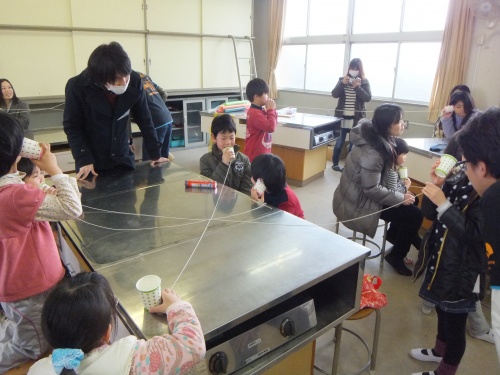11月に来校していただいた平松さんや劇団の方々からお手紙をもらっていました。
卒業を目の前にひかえた6年生のみなさんに,ぜひ読んでもらいたいと思います。
教頭先生,H先生,S先生,その他昨年の朗読劇『沙也可の見た空』でご協力頂いた皆様,寒中お見舞い申し上げます。その節はありがとうございました。
観劇感想文ありがとうございました。皆で読ませてもらって,感動しました。そこで我々も何かお返しがしたいということでお礼文を書かせて頂きました。
本年も是非川永小学校公演に訪れたいと一同思っています。本年も宜しくお願い致します。
校長先生にも宜しくお伝えください。
【平松組脚本・演出 平松 豊司】
川永小学校6年の皆さん,お元気ですか。
寒中お見舞い申し上げます。
平松組脚本・演出の平松豊治です。朗読劇『沙也可の見た空』の観劇感想文ありがとうございました。色んなことを感じて貰えて嬉しいです。今こうやって自分の卒業した小学校に戻って来られて感激しています。
沙也可は自分の意思を生涯貫いて生きました。皆さんもこれからの人生色々なことがあると思います。楽しいことばかりではなく,辛いことにも遭遇します。もし大きな壁にぶち当たったら,沙也可のことを思い出してください。そして,周りの声に惑わされずに自分を信じて壁を乗り越えてください。そんな皆さんの姿をみて,きっと手を差し伸べてくれる人が現れます。何事も諦めないでくださいね。諦めたらそこで終わってしまいます。
ここで少し脚本と演出の仕事の説明をしたいと思います。脚本は役者が喋る台詞が書かれたもので,いわば映画やドラマの設計図です。さて演出です。その設計図を具体化するには,建築と一緒で映画や舞台をつくる場合,そこには様々な役目の人達が関わるこことになります。役を演じる役者,その役者を支える照明さんや,音声(音響)さんなどのスタッフです。
だから現場では,色んな意見やアイデアが出てきます。簡単にいうと,そんな時に現場が混乱しないようにまとめる役目が演出です。いわば船の船長ですね。
船長が目的地が分かっていなければ,船は大海原で迷い沈没してしまうかもしれません。だから演出家はどんな作品にしたいのかというしっかりとした考えを持っていなければいけません。
皆さんの中には将来役者や声優,歌手などの芸能の仕事をしたいと思っている人もいるかもしれません。厳しい世界ですが,こんなに素敵な仕事はありません。もし将来どこかの現場で会ったら,あの時沙也可を観たと言ってくださいね。そんな日が来ることを楽しみにしています。
【平松組脚本・演出 平松豊治】
この度はみんなの感想文を読ませて貰って心から感動しました。
沙也可役の今村博信です。
みんなの学校に行くのは3回目になります。今までの2回はお芝居の体験レッスンみたいな感じでしたが,今回は初めてお芝居を観てもらおうという事になりました。
どう思ってくれたかなと,凄く不安でしたが感想文を読ませて貰って,みんなが楽しんでくれていて本当に安心しました。
何故かというと,みんなが教室に入っているときに準備室で待っていたのですが,緊張でドキドキしていました。

言葉や歴史の事も難しくて分かってもらえるかなぁ,セリフを間違えないように言えるかなぁ,みんな途中で飽きちゃわないかなぁ,とか不安でいっぱいでした。
でも感想文を読ませて貰って,「迫力が凄かった」,「歴史が好きになった」,「泣きそうになった」などの感想が多くて心がいっぱいになりました。
本当にありがとうございました。
「沙也可の見た空」の東京公演も決まりました!
和歌山の広くて,やさしい空を想いながら,東京の空の下でもお客さんに和歌山の空を届けられるように,,一生懸命がんばります!
今年も和歌山に行きますので,宜しくお願いします!
感謝!!
【今村博信】
川永小学校の6年生の皆さん。
寒中お見舞い申し上げます。
昨年の朗読劇『沙也可の見た空』にてお会いしたRICOです。
皆さんの感想文を読ませて頂きました。ありがとうございました。
それぞれに色んな感想を持ちながら,本当にちゃんと観て聴いて下さったんだぁと感謝しております。
私達も一生懸命演じました。その分皆さんも本当に一生懸命に視聴して下さった事に感動を覚えます。
私はこの作品に出合うまで,雑賀孫市の事も,沙也可の事も全く知りませんでした。

いつも私は演じる事を通して新しい発見や出会いがあります。
今回は皆さんにも出会うことが出来ました!
歴史に興味を覚えた方,芝居,朗読,音楽に興味を持った方,様々に新たな発見があったのならばうれしいです。
私達役者も皆さんにそんな橋渡しが出来たとしたならば最高です!
今年,皆さんは小学校を卒業し,4月には中学生になるのですね。
大人への道のりの第一歩!
これから数えきれないほどの色んな出会いが待っています。
どうか,そんな出会いを大切にして沙也可のように勇気ある優しい心を持った人に成長していって下さい。
今回の芝居が,皆さんの小学校生活の思い出の一ページになれば嬉しいです。
皆さんにとって,今年が去年よりも更に良い一年になりますように!
【RICO】
川永小学校6年生の皆さん,感想文ありがとうございました。
パーカッションが持つ表現力は無限大だと私は思っており,その可能性を引き出して更に楽しんで頂けるように演奏していくのが私の役割でもあります。今回,朗読の魅力に加え,感受性豊かな皆さんにパーカッションの魅力が共に伝わってくれたようで,大変嬉しいです。
今回使用したのは私が持っている楽器のまだまだほんの一部ですが,それぞれ個性ある楽器たちを揃えてセットを組みました。どの楽器もその楽器にしかない魅力があります。児童の皆さんも,一人一人違う,だからこそ面白い,個々の個性を大切に自分を表現していってほしいと願っております。
ではでは,お元気で!
【皆さんの輝かしい未来を応援する亞希より】
川永小学校のみなさまへ
先日は平松組の朗読劇をご覧下さり,ほんとうにありがとうございました。
そして,個性あふれる素晴らしい感想文を書いて下さったこと,感謝の気持ちでいっぱいになりました。
様々な視点から,想像もつかない感想や,楽しそうな感想,発想には,とても感動してしまい,読みながら,正直泣けてきてしまいました。そして,心が洗われ,また,頑張ろう!…と,パワーを頂いてしまいました。私が言うのもおかしいかもしれませんが,平松組のメンバー全員,とても良い方ばかりで,そのメンバーと皆様の前で朗読劇をさせていただいた事,ほんとうに嬉しさでいっぱいでした。

もしよかったら,また,川永小学校で,朗読劇やらせてくださいね。
みなさま,お元気で!また,お会いしましょうね。ほんとうにありがとうございました。
【ピアノ&ピアニカ 樫村 直樹】
川永小学校6年生の皆様へ。
「沙也可の見た空」の公演感想文,ありがとうございました。
小学生とは思えない,鋭い観察眼にはビックリしました。皆さんからお寄せ頂いた感想文は,鋭い指摘の中にも,とてもあたたかく,ほのぼのとしていて,皆さんに一番に観て頂いて良かったと,本当に心からそう思いました。皆さんの感想文は今以上に勉強して,稽古して,みなさんにもっと喜んで貰える作品に仕上げて行かなければと…,私に力を与えてくれました。
川永小学校の皆さん!ありがとう!喜んでくれてありがとう!
又,機会があったら皆さんにお会いしたいです。
元気でね!
【桔梗】
川永小学校のみんな,元気ですか?
お久し振りです,阿部です。11月にみんなの前で何だかよくわからい事をいっぱい喋っていたヤツです。みんなの感想文,お芝居をしたメンバーで読ませてもらいました!みんな感動しながら読みましたよ!!
ああいうお芝居(あの時は朗読劇でしたが)を見ることがほとんどないと聞いて僕らはちょっとショックでした。
テレビをつければ毎日ドラマが見られますが,そういう芸能人さんたちもよく舞台に立ったりお芝居をしたりするんです。あの日の僕たちみたいに。
何が言いたいかっていうと,本当は舞台やお芝居って芸能人が出てようが出てなかろうが,もっと身近なものなんだっていうことなんですね。そう,川永小学校のみんなだって…。
あの11月,僕ら俳優たちが演じているのをみて「ワクワクした」または「ドキドキした」っていう人はいますか?
みんなで話し合うのが恥ずかしかったら,そっと自分の胸にだけ,そう,心の奥底にある自分の,自分だけの気持ちに聞いてみてほしいと思います。
そしてもし,ワクワクドキドキしたという人がいるにならば…。断言しましょう,そんな貴方には「俳優の才能がある」のかもしれません。
これから先,みんなには色んな「可能性」と「選択肢」があります。もしもその時にふと,「演劇」や「芝居」,「俳優・女優」ということが頭に浮かんだならば,そんなときは僕の書いたことを思い出してみてください。そのとき,ワクワクやドキドキがあったならば… もしかしたらね。
人生,これからは辛いことや苦しいこと,悲しいことがあっても,基本的には楽しいことに変えられます。
みんなより20年くらい多く生きていますが,自分で楽しくしていこうと思っていればまず間違いないですよ。これは断言しておきます。
みんなのこれから先の人生が,ぜひ素晴らしいものになりますように。 またね。
【阿部 悠磨】