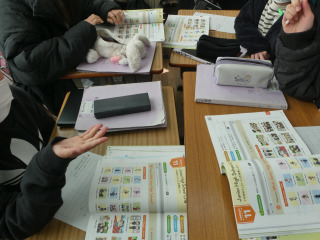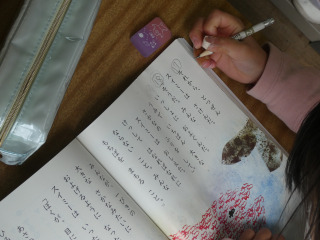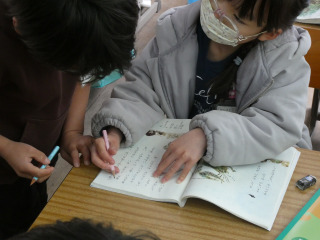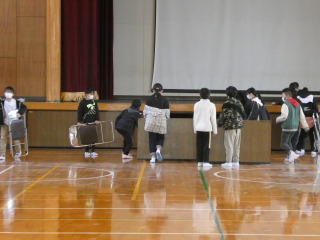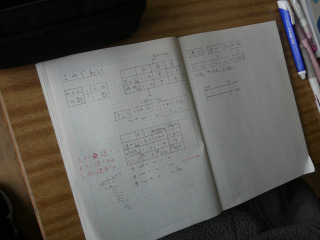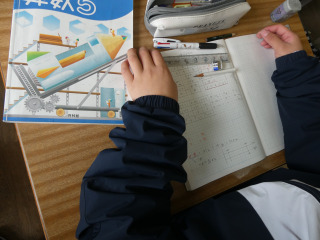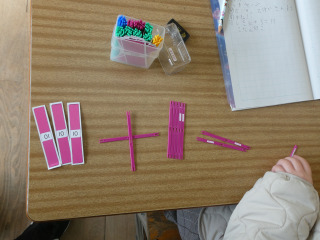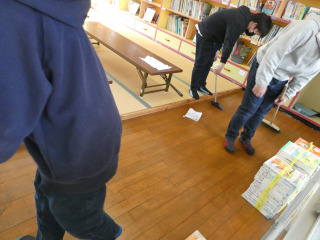子ども(18歳未満)を取り巻く様々な相談に対応するため、平成22年4月に、「家庭児童相談室(福祉事務所)」と「子ども支援センター(教育委員会)」が融合し、こども総合支援センターが発足しました。
●子どもに関する相談
子育てや教育上の問題など、子どもに関する様々な問題について相談に応じます。
●不登校の子どものための適応指導教室(ふれあい教室)
児童・生徒が安心して過ごせる場を提供し、友達とのふれあいや学習を通して、学校復帰をめざして取り組みます。
●日本語指導のサポート
帰国子女や外国籍の子どもの日本語の学習等をサポートします。
●母子生活支援施設入所事業
18歳未満の子どもを育てている母子家庭等の母親で、生活と子育ての支援を必要とする方の自立をお手伝いします。
●入院助産制度の実施
保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由で入院助産を受けることができない方に対し、出産費を援助する制度です。
●ショートステイ事業
保護者の方が病気などの時に子どもを一時的にお預かりします。
●夜間養護事業(トワイライトステイ)
夜勤や休日出勤などの時に子どもを一時的にお預かりします。
●里親助成事業
里親間の連絡強化、技術の向上を目指します。
●養育支援訪問事業
育児に不安を持っている家庭を定期的に訪問して、育児ストレスの緩和を図ります。
和歌山市こども総合支援センター TEL.073-402-7830
和歌山市北桶屋町7番地