また、表彰状が届きましたので、全園児が集まった、3月の誕生会の後で、わたしました。
図画の賞状です。



おめでとうございます。
4歳のみんなが、丁寧に作品を作り上げていました。
写真のフレームです。





集中力が育っている時間のように、ボンドをつけて、そこに貼る形を丁寧に乗せるという作業を繰り返していました。
10時より全員が遊戯室に入り、「ひな祭り会」が行われました。
先生から、ひな祭りのことを教えてもらいました。そのあと、ひな祭りに関係したお話を、先生全員が一人一役を演じて楽しみました。





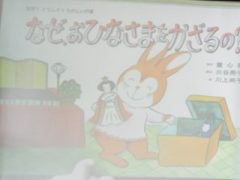



歌も歌いました。
さいごに、ひなあられを一人一人もらって、部屋に戻りました。
お部屋では、冷えたおいしいおやつが「おひなさまゼリー」をいただきました。
エプロンシアターと、紙芝居、手品と、いろいろと手を変え品を変えというように、子供たちの気持ちを引きつけながら、食べ物の大切さを伝えてくださいました。
子供たちは、興味がありずんずんと、座っている場所から、前に近づいていってました。楽しい時間でした。





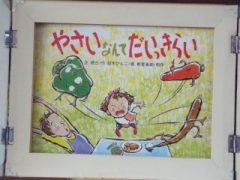


地域の方ということで、特にお礼もお菓子だけということで、記念として、演技をされている写真をもらっていただきました。本当にありがとうございました。