プールの東側にある名草川沿いに茂っていた樹木を伐採(和歌山市が業者に委託して伐採)してくださいました。
見通しも風通しもよくなりました。ありがとうございました。


お知らせ
玄関のメダカたち
玄関の水槽でメダカを飼っています。
5年生の子供達が、メダカに名前をつけてくれており、その紹介を手描きで紹介してくれています。
下の学年の子供達が楽しげにいつも見てくれています。
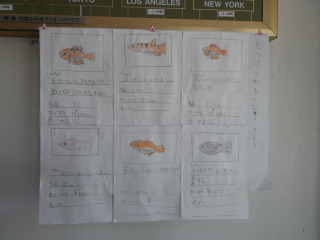

【6年】1学期末教室ギャラリー
教室の後方の掲示スペースには、子供達の作品が掲示されています。
子供達が一生懸命頑張った作品を紹介します。
写真が小さすぎて分かりづらいかもしてませんが…


【委員会】保健委員会の7・8月掲示
保健委員会の子供達が、全校の皆さんに啓発している保健室前掲示。
7・8月は、「おやつで栄養補給・リフレッシュ」の呼びかけをしています。
掲示しているヒマワリは、6年生を中心に子供達が紙を折って作ってくれました。
引き続き、ウルシに注意の呼びかけもしていました。

【5年】1学期末教室ギャラリー
教室の後方の掲示スペースには、子供達の作品が掲示されています。
子供達が一生懸命頑張った作品を紹介します。
写真が小さすぎて分かりづらいかもしてませんが…


【2年】町たんけん
2年生が町たんけんをしたときに「JAわかやま 和田川支店」さんに立ち寄りお話を伺いました。
丁寧に説明してくださったので、子供たちが感謝のメッセージを届けたところ、支店内に掲示してくださいました。
まちたんけんのときの写真も届けてくださいましたので、紹介します。


【4年】1学期末教室ギャラリー
教室の後方の掲示スペースには、子供達の作品が掲示されています。
子供達が一生懸命頑張った作品を紹介します。
写真が小さすぎて分かりづらいかもしてませんが…


【参考】LGBTQ相談窓口について
和歌山県男女共同参画センター“りぃぶる” では、レズビアン(L)・ゲイ(G)・バイセクシャル(B)・トランスジェンダー(T)など、様々な性的指向や性自認の方のための、電話または面接による専門相談窓口を開設しています。(事前予約制)
本人からの相談だけでなく、ご家族や友人、職場の関係者など周りの方からの相談も受けることができます。
「秘密厳守、匿名での相談も可能ですので、安心してご相談ください。」とのことです。
詳しい説明資料は、こちら。
【3年】1学期末教室ギャラリー
教室の後方の掲示スペースには、子供達の作品が掲示されています。
子供達が一生懸命頑張った作品を紹介します。
写真が小さすぎて分かりづらいかもしてませんが…

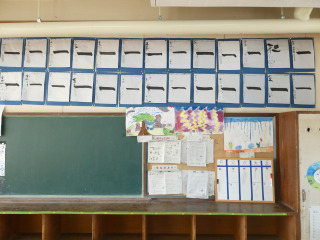
【参考】夏休み期間における河川水難事故防止について
安全に楽しく川や水辺で活動するために活用を図っていただき、水難事故の防止にお役立ください。
普及啓発・学習ツール
① 子ども向け学習冊子・アプリ 「うんこドリル 川の安全」
(水管理・国土保全局 河川環境課・公営財団法人 河川財団 監修、文響社 発行)
冊子: https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/pdf/unnkodoriru.pdf
WEB アプリ:https://play.unkogakuen.com/manabi/game/river/?rf=drill
② 小学生向け水難事故防止動画 「リバーアドベンチャー ~川に魅せられし者たち~」
(水管理・国土保全局 河川環境課 作成)
https://www.youtube.com/watch?v=IrIkZCm11l0
③ 水難事故防止に取り組む6団体が協働で制作 「水辺の安全学習アプリ」
(公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 公開)
https://mizube-anzen.jp/
④ ~MIZUBE ASOBI GUIDE~(水管理・国土保全局 河川環境課 作成)
http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/pdf/mizubeasobiguide.pdf
⑤ 「水辺の安全ハンドブック」((公財)河川財団 作成)
https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid129.html
⑥ No More 水難事故((公財)河川財団 作成)
https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid324.html
⑦ 川遊び安全ノート「えんじょいリバー」((公財)河川財団 作成)
http://www.kasen.or.jp/Portals/0/pdf_mizube/enjoyriver.pdf
全国の水難事故マップ((公財)河川財団 作成)
http://www.kasen.or.jp/mizube/tabid118.html

