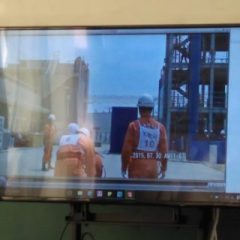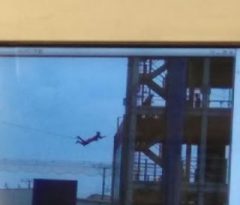11月5日(金)
1年生から5年生が秋の遠足にでかけました。
絶好の遠足日和のもと、楽しい1日を過ごしたことと思います。
●1年生は加太の町・加太小学校








●2年生は磯ノ浦・河西公園








●3年生は県立博物館・海南nobinos








●4年生は稲むらの火の館・道成寺








●5年生は白浜エネルギーランド・湯浅醤油








11月5日(金)
1年生から5年生が秋の遠足にでかけました。
絶好の遠足日和のもと、楽しい1日を過ごしたことと思います。
●1年生は加太の町・加太小学校








●2年生は磯ノ浦・河西公園








●3年生は県立博物館・海南nobinos








●4年生は稲むらの火の館・道成寺








●5年生は白浜エネルギーランド・湯浅醤油








8月2日(月)は登校日でした。
(この記事を書いているのは8月3日ですが、朝からの激しい雷雨が昨日でなくてよかったと思いました。久しぶりの雨は、校庭の芝生をはじめ植物にとっては恵みの雨ではあるのですが、雷は怖いです。)
朝から暑い中での登校でしたが、みんな元気に登校できていて何よりでした。
朝の掃除を終えたあとは、それぞれの教室で10時半の下校まで、友達と話をしたり、宿題の答え合わせをしたりして過ごしました。
夏休み中ではありますが、どのクラスの子供たちも落ち着いて過ごしていました。


1年生はシャボン玉も楽しみました。


学年によっては、7月の夏休み中に実施した、タブレットを使ったアンケートの結果を子供たちに発表したり、子供たちが各家庭からタブレットを使って投稿した写真を紹介したりしていました。
タブレットについてはまだまだ取り組み始めたところでよくわからないところもあるかと思いますが、子供たちは使いながら慣れていくのだと思います。よりよい活用を目指して学校も取り組んでいきますので、今後ともご協力をお願いいたします。
ちなみにこの日の午後は、職員もタブレットの研修を行いました。

16時からは、6年生保護者対象に「修学旅行説明会」も行いました。
お忙しい中、また暑い中お越しいただきありがとうございました。
9月6日、みんなで元気に出発できることを願っています。
20日あまりの夏休み、けがや事故に十分気を付けて、元気に過ごしてください。
次の登校は、2学期の始業式(8月25日)です。
7月24日(土)13時~
『スタンプラリーin貴志南まつり』が開催されました。
祭りについては、昨年度は実施できなかったのですが、今年度はできる範囲で実施しようと、育友会の役員さんや部員さんを中心に企画・運営してくださいました。特に、感染対策はかなり徹底して行っていただきました。
また、本日のみならず、これまでの準備にたくさんの時間を使っていただいています。
子供たちのためにご尽力いただき、本当にありがとうございました。
スーパーボール、1円玉おとし、射的、的あて、千本引き、輪投げ、魚つり、をスタンプラリー方式で回りました。
たくさんの景品をGETして、お土産一杯持って帰っていった子供たち。
祭りをとっても楽しみにしていた子供たちですが、きっとみんな満足して参加できたかなあと思います。
スーパーボール


1円玉落とし


射的


的あて


千本引き


輪投げ


魚釣り


その他祭りの様子





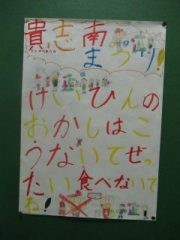




関わってくださった多くの皆様、ありがとうございました!
朝からの雨と風の中、1年・2年・4年がバスに乗って県立博物館に出かけていましたが、
11時半ごろ、無事に学校に戻りました。
雨のため、午前中だけという短い時間でしたが、
帰ってきた子供たちは
「楽しかった~」「カメとか、サメとか見た」
「校長先生の背くらいのエイもいた」など、いろいろ教えてくれました。
1年生はみんな「おなかすいた~」と帰ってきたので、いつもより少し早めの昼食となっています。
お弁当づくりや、天候の心配など、さまざまな面でご協力いただきありがとうございました。
4月8日(木)
いよいよ新年度のスタートです。
今日は「新任式」と「始業式」を、運動場で行いました。
まだまだいつのもようには戻りませんが、対策をしながらできることをやっていきたいと考えています。
子供たちは、新クラスの担任とともに、気持ちを新たにがんばろうとしています。
今年もどうかよろしくお願いいたします。
10月27日(火)、4年生がネットモラルの出前授業を受けました。
講師は、和歌山市少年センターの西嶋先生です。
今の時代は、携帯やスマホ、タブレット、通信できるゲーム機器などは、子供たちにとって日常的に関わるものとなってきています。そのような中、それらを「使わない」のではなく、「正しく使う」ことを教えていただきました。
和歌山県は、日本一フィルタリング率が低いのだそうです。(子供が自由にいろんなところにアクセスできてしまうということです)
また、小学生でも、ネット上で知らない人とやりとりしたり、知らない人に実際に会いに行ったりすることも多くなってきているそうです。これは大変危険なことにつながっていきます。
ご家庭でもぜひ、携帯やスマホの使い方、ゲームの遊び方など、お子さんとお話してみてください。


4年生の社会では、ごみについての学習をしています。
その学習の一環として、本日、和歌山市環境部より出前授業に来ていただきました。
5時間目は、体育館にて、「3Rでごみげんりょう」というお話を聞かせていただきました。
「3R」は、「Reduce(リデュース)」、「Reuse(リユース)」、「Recycle(リサイクル)」のことです。


6時間目は、実際にパッカー車に来てもらい、ごみを入れたり出したりする様子も見せていただきながら、ごみについて学習しました。
暑い中、2時間続きの学習でしたが、4年生の子供たちはどの子も皆、熱心に聞いていました。
「5ページメモとったよ」という子がいたり、多くの子が次々と質問できていたり、
出前授業の先生からの質問にも積極的に手を挙げて答えていたりと、とても意欲的に学習できていました。




12月3日(火)
橋本市の中学校から大前先生が4年生の子どもたちに授業をしに来てくれました。この先生は視覚障碍がありますが、社会科の先生として勤めており、本校の4年生担任の先生の知り合いでもあります。以前も4年生に授業をしに来てくれました。物が見えないとどんな不便があるのか、そのためにどんな工夫や対処をして生活したり仕事をしたりしているのかを、体験を通して教えてもらいました。問題や要点などは黒板の代わりに、モニターにパソコンで打って子どもたちに見せます。キーボードを打つと同時にパソコンがしゃべるのにまずビックリ。点字もすらすら読んでみせてくれたのにもビックリ。今はスマホに音声認識や音声案内のアプリがあるので便利だとのこと。2クラス合同で2時間の予定が、けっこう延長しましたが、それでも子どもたちの興味は尽きませんでした。きっとクラスメイトの子と重ね合わせて聞いていたのでしょう。大前先生の言葉「何かお手つだいすることありませんかと話しかけてくれると嬉しい」の言葉を感想文に書いている子が多かったのもなるほどです。

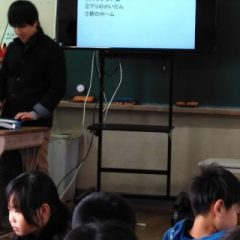

11月5日(火)
法務局の人権擁護委員さんが人権教室の出張授業をしてくれました。内容はいじめ防止です。この前は2年生と6年生が警察関係の先生から法的な観点からかみくだいて教えてもらいましたが、今回は「人権」の観点からの指導です。友達同士の誕生プレゼントが発端でいじめが始まるという内容のDVDを見て話し合いました。1組でも2組でも、みんな他人事でなく、自分事として真剣に考えることができました。




10月30日(水)
4年生は、社会で「安全なくらしを守る」の単元を学習しており、そのまとめとして今日は消防士さんに来ていただいて2クラス合同で話を聞きました。この消防士さんは、2年生の子のお父さんで、校長先生の元教え子でもあります。救命の仕事や訓練について詳しく話してくれました。訓練の様子は動画を用意してくれていて、その厳しさがよく伝わりました。また、最後は質問コーナーがあり、いろいろな質問が飛び出しました。その中で「1秒でも早く搬送することが命を守ることにつながる」とか「火事の時は、煙で前が見えない状態で手探りで進むのと、マスクのボンベの酸素残量が減って呼吸しづらくなるのは、今でも怖いと感じる」の話が心に残ったようです。人の命にかかわる現場に出動する消防士は、体力的にも精神的にもタフであることが求められることを、子どもたちは感じ取ってくれたことでしょう。