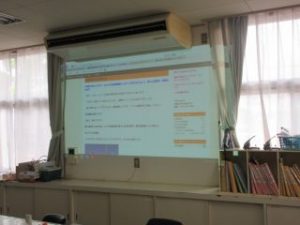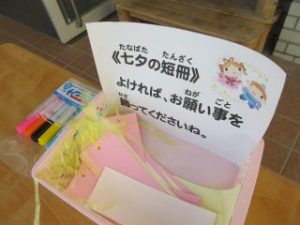沿革の概要:園の歴史を振り返る機会としたいですね。
昭和23. 7.10 私立中之島幼稚園として発足 園児数150名(職員数5名)で開園
中之島小学校3教室借用
25. 4. 1 和歌山市立中之島幼稚園として認可 4学級編成
26.11.30 市幼稚園協会委託研究発表会開催
27. 4. 1 1学級増 5学級編成
6. 6 1保育室 物置増築
28. 4. 1 2学級増 7学級編成 専任園長発令
12.26 2保育室増築
29. 2.13 市教育委員会委託音楽リズム研究発表会開催
4.24 便所 廊下増築
30. 7.15 1保育室増築 玄関 築山 花壇 禽舎新設
33.12.25 1保育室増築
34.11.16 正門新設
11.20 近畿放送教育研究発表会(第3回)開催
35. 9. 3 園舎東側にフェンスをとりつける
37. 3.12 職員室増築
39. 4. 1 2学級増 9学級編成
40. 4.15 南側便所増築
7.22 プール東側へ遊び場拡張
41. 4. 1 1学級増 10学級編成
11. 4 近畿視聴覚研究会(第16回)開催
42.11. 1 西棟園舎(3保育室)新築
45.11.12 市教育委員会委託健康教育研究会開催
48.11. 1 手洗い場増設
51. 8.31 園舎改造(東棟北より5教室廊下を撤去し拡張工事)
52.11. 8 県・市教育委員会委託幼稚園教育研究会開催
55. 4.11 学級減 9学級編成
7.22 全国国公立幼稚園教育研究協議会(第27回)和歌山大会会場園となる
57. 4. 1 3学級減 6学級編成
58. 1.11 中庭テラス増設
62. 6.15 園舎改築工事竣工式
7.11 園歌碑建立
11.13 県学校体育研究会(幼稚園部会)開催
63. 4.11 1学級減 5学級編成
平成 元. 4. 1 1学級減 4学級編成
元. 5. 8 給食実施(週4回)
2. 2.23 平成4年度放送教育研究会全国大会(和歌山大会)の委嘱を受ける
3. 3.18 遊戯室の一文字幕完成する
3.11.16 プレハブ物置3ヶ所設置する
4.11.13 第43回放送教育研究会全国大会(和歌山大会)会場園となる
5.10. 4 預かり保育実施する(希望者のみ3時まで)
8. 8. 2 スクール・ドリームプラン(砂場.畑の増設)
9. 6. 6 スクール・ドリームプラン(植木鉢作り.寄せ植え.壁画製作.葉ボタン栽培)
10.11. 末 中之島幼稚園壁画完成.あゆみパンフレット作成
10.12.13 創立50周年式典,祝賀の会を挙行する
11.10. 6 砂場西側フェンス取りつける
11.11.11 市教育委員会委託幼稚園教育研究会開催
12. 2.17 第33回市視聴覚教育研究発表会開催
13. 4. 1 1学級増(3歳児)
15. 2.21 遊戯室に空調設備設置
15. 4. 1 文部科学省より平成15・16年度就学前教育と小学校の連携に関する総合的調査研究につい ての指定を受ける
16. 3.23 給水管改修設備工事
16.11.18 文部科学省指定 就学前教育と小学校の連携に関する総合的調査研究発表会開催
18. 2.16 第39回市視聴覚教育研究発表会開催
18.10.18 総合遊具の修繕工事(既設登り棒撤去・手摺縞板・クサリ溶接・落下防止ネット取付け)
19. 3.29 鉄棒下及び滑り台降り口登り口に安全対策としてのソフトマットを設置
22. 3.15 滑り台降り口に安全対策としてのソフトマットを設置
23. 4.29 総合遊具滑り台階段下に安全対策としてのソフトマットを設置
26.11.22 和歌山市指定 幼小学びのアプローチカリキュラム推進事業 研究保育開催
27. 1.10 2階、5歳児保育室(もも・さくら)に空調設備設置
28. 2.21 1階、3歳児保育室(ばら)に空調設備設置
28.11.22 平成28年度 体力・保育力アップモデル校保育研究大会兼第56回学校体育研
究大会和歌山大会プレ大会 研究保育開催
29. 5.14 1階、4歳児保育室(きく・すみれ)に空調設備設置
29. 5.28 幼稚園園庭北側に防球ネット設置
29.11.10 第56回全国学校体育研究大会和歌山大会において研究保育開催
令和 1. 6. 図書室に空調設備設置
1. 7. 地震による倒壊をさけるため、園の周りの塀の取り換え
2. 7. 水遊びのためのミスト発生機のとりつけ